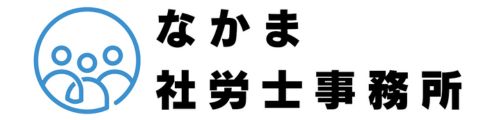「休憩」を徹底解説
こんにちは。今回は労働基準法で定められている「休憩」について取り上げます。
「休憩はお昼の1時間だけ与えればいいの?」「外出していいの?」「シフト制ではどう扱う?」など、現場からよく質問があるテーマです。
この記事では、休憩に関する労基法上の基本ルールと、実務上の注意点を整理します。
労基法における休憩の基本ルール
労働基準法第34条では、休憩について次のように規定されています。
- 使用者は、労働時間が6時間を超える場合には少なくとも45分、8時間を超える場合には少なくとも1時間の休憩を労働時間の途中に与えなければならない。
- 休憩時間は自由に利用させなければならない。
- 休憩時間の与え方については一斉付与が原則。ただし労使協定で別段の定めをした場合は例外も可能。
ポイント整理
- 労働時間6時間超 → 45分以上の休憩
- 労働時間8時間超 → 60分以上の休憩
- 休憩は労働時間の途中に与える必要がある
- 休憩は「自由利用」が原則
実務で問題になりやすい「自由利用」
休憩は労働者が自由に使える時間でなければなりません。
経営者の立場で誤解しやすいのが以下の点です。
- 電話番や来客対応をさせる
→ 労働から解放されていないため「労働時間」とみなされます。 - 外出を一律禁止している
→ 「自由利用」に反する可能性があります。安全上の理由で一部制限するのはOKですが、合理的な説明が必要です。
一斉付与の原則
労基法は「一斉に休憩を与えること」が原則です(34条3項)。
これは、工場などで一斉にラインを止めて休憩をとらせることを想定しています。
しかし、接客業などでは全員が同時に休憩に入ると業務が回りません。
そのため「一斉付与しない」ことを労使協定で定めることで、交替制の休憩をとらせることが可能です。
実務上よくある質問と注意点
Q 労働時間が6時間ちょうどの場合、休憩は必要ですか?
→ 必要ありません。 労基法は「6時間を超える場合」に休憩を義務付けています。
ただし、6時間1分働かせると45分必要になりますので注意してください。
Q 「30分休憩+30分早上がり」で調整してもいいですか?
→ NGです。 休憩は必ず労働時間の途中に与える必要があります。
「休憩を削って早く帰らせる」は休憩の代替になりません。
Q 休憩を15分×4回に分けても大丈夫?
→ 問題ありません。 合計で法定休憩時間を満たし、労働時間の途中に与えればOKです。
ただし、細切れにしすぎると「実質的に休めない」と評価される可能性もあるので、実態を重視しましょう。
Q 夜勤(深夜労働)の場合は休憩を増やす必要がありますか?
→ 法定休憩時間は日勤と同じですが、深夜労働は疲労が蓄積しやすいため、実務的には短い休憩を複数回与えるなどの工夫が望ましいです。
Q 休憩中に「電話が鳴ったら出て」と指示しているけど大丈夫?
→ 労働時間とみなされる可能性が高いです。
Q 勤務シフト上、全員同時に休憩をとるのが難しい。どうすればいい?
→ 労使協定を締結すれば、交替で休憩を取らせることが可能です。
協定がなければ「法違反」になりますので注意が必要です。
Q 休憩を1時間与えているけど、実際には30分で仕事をしている社員がいる。問題?
→ キチンと指導しましょう。
会社が仕事をしていることを把握していながら指導しなかった場合、労働時間にカウントされる可能性があります。
トラブル防止のためには「休憩中は作業禁止」を徹底、指導することが大切です。
まとめ
労基法の休憩に関するルールは一見シンプルですが、現場運用では誤解や違反が起こりやすい分野です。
特に「自由利用」の扱いは、実務上の落とし穴になりがちです。
運用などでお困りごとがござましたら、お気軽にご連絡くださいませ。