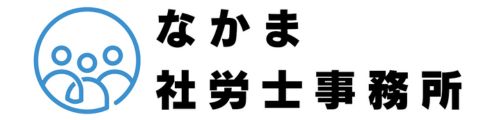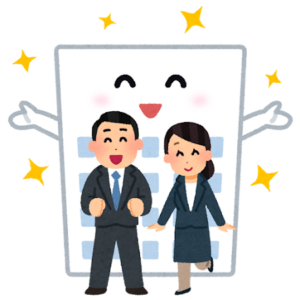年次有給休暇の基本と実務対応のポイント
こんにちは。なかま社労士事務所の中間です。
今回は「年次有給休暇(以下、有休)」について、制度の基本から実務上の注意点まで、わかりやすくご紹介します。労務管理を行う上で避けて通れないテーマですので、ぜひ最後までご覧ください。
目次
年次有給休暇とは?
年次有給休暇とは、労働基準法第39条に基づき、一定の条件を満たした労働者に対して、会社が賃金を支払いながら休暇を与える制度です。目的は、労働者の心身の疲労回復と生活のゆとりの確保にあります。
有給休暇の付与要件
有休が付与されるには、次の2つの条件を満たす必要があります。
- 継続勤務6か月以上
- 全労働日の8割以上の出勤
つまり、入社してから6か月間継続して勤務し、その間に8割以上の出勤があれば、10日間の有休が付与されます。
付与日数の推移
有休の日数は、勤続年数に応じて以下のように増加していきます。
週5日勤務・年間所定労働日数が217日以上の場合の例
| 勤続年数 | 付与日数 |
|---|---|
| 6か月 | 10日 |
| 1年6か月 | 11日 |
| 2年6か月 | 12日 |
| 3年6か月 | 14日 |
| 4年6か月 | 16日 |
| 5年6か月 | 18日 |
| 6年6か月以上 | 20日 |
パート・アルバイトのための比例付与日数表
| 継続勤務年数 | 週所定労働日数1日(年所定労働日数48~72日) | 2日(年所定労働日数73~120日) | 3日(年所定労働日数121~168日) | 4日(年所定労働日数169~216日) |
|---|---|---|---|---|
| 6か月 | 1日 | 3日 | 5日 | 7日 |
| 1年6か月 | 2日 | 4日 | 6日 | 8日 |
| 2年6か月 | 2日 | 4日 | 6日 | 9日 |
| 3年6か月 | 2日 | 5日 | 8日 | 10日 |
| 4年6か月 | 3日 | 6日 | 9日 | 12日 |
| 5年6か月 | 3日 | 6日 | 10日 | 13日 |
| 6年6か月以上 | 3日 | 7日 | 11日 | 15日 |
有休の時効と繰越
有休の有効期限は 2年間 です。付与された日から2年を過ぎると、未使用の有休は 自動的に消滅 してしまいます。
例えば、2023年4月1日に付与された有休は、2025年3月31日までに使用しなければ消滅します。
また、有休は最大で翌年に繰り越せますが、その翌年になると古い分から順に消えていきます。労働者への周知と管理が大切です。
年5日の取得義務(2019年法改正)
2019年4月の法改正により、 年10日以上の有休が付与される労働者に対して、年5日の取得が義務 となりました。
企業は、対象となる労働者に対して、以下のいずれかの方法で年5日の取得を確保する必要があります。
- 労働者が自ら申請して5日取得する
- 会社が時季指定して5日取得させる
- 計画的付与制度により5日を消化する
この義務を怠ると、1人につき30万円以下の罰金となる可能性があります。実務上も非常に重要なポイントです。
時季変更権とその制限
労働者が有休の取得を申し出た場合、原則として会社はこれを拒否できません。ただし、以下のように「事業の正常な運営を妨げる場合」に限って、時季変更権を行使できます。
- 同じ日に多数の従業員が取得を希望し、業務が回らなくなる場合
- 特別な繁忙期など、業務に支障が出るとき
ただし、時季変更権は「他の日に取得させること」が前提です。有休そのものを拒否することはできません。
計画的付与制度とは?
有休の取得を促進する制度として、「計画的付与制度」があります。これは、5日を超える有休について、会社側が計画的に取得日を割り振る制度です。
以下の方法で導入可能です
- 会社全体で一斉に休む(例:夏季休暇、年末年始)
- 部署ごとに計画を立てる
- 個人別に取得計画を立てる
労使協定を結ぶ必要がありますが、年5日の取得義務への対応にもつながります。
有休管理簿の作成義務
2019年の改正により、有休を付与した企業には「有休管理簿」の作成が義務づけられました。
管理簿には以下の情報を記載する必要があります。
- 付与日
- 付与日数
- 取得日とその日数
- 残日数
これらの記録を 3年間 保存する義務があります。Excel等で作成しても問題ありませんが、勤怠管理システムなどを活用することもおすすめです。
時間単位の有休制度
1日単位や半日単位だけでなく、 時間単位で有休を取得できる制度もあります(年5日分の範囲内)。
導入には 就業規則への記載と労使協定の締結が必要です。家庭の事情や通院、保育園の送迎など、短時間の用事に対応できるため、従業員満足度の向上にもつながります。
実務での注意点
実際の運用にあたっては、以下の点に特に注意が必要です。
- 取得義務5日のカウント漏れに注意する(時間単位や半日も合算)
- 有休取得を事実上制限するようなルールや雰囲気は法令違反につながる
- パート・アルバイトも要件を満たせば付与対象になる
- 有休の買い取りは原則禁止(ただし退職時の未消化分は例外)
まとめ
適切に運用していくために、就業規則をきちんと整備し、労使双方納得いく形で、適切な付与・取得管理を行うことが、労働環境の改善とトラブル防止に直結します。
特に2019年の法改正以降は、年5日の取得義務や有休管理簿の義務があり、対応が不十分な場合は罰則も場合によってはあります。
なかま社労士事務所では、有休管理の整備や労使協定の作成、就業規則の見直しもサポートしています。ご不明な点があれば、お気軽にご相談ください!