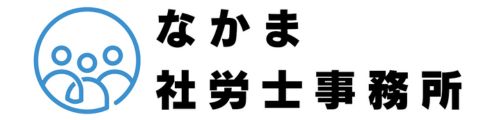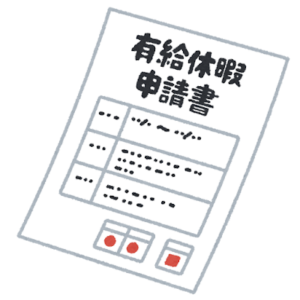柔軟な働き方のカギ「フレックスタイム制」とは
こんにちは。なかま社労士事務所の中間です。
今回は、働き方改革の一環として注目されている「フレックスタイム制」について詳しく解説します。
社員のワーク・ライフ・バランスを高め、生産性の向上にもつながる制度ですが、導入・運用にはしっかりとした制度設計と注意が必要です。
この記事では、制度の基本、導入手順、具体的な記載例、さらに実務上の注意点まで丁寧にご紹介します。
目次
フレックスタイム制とは?
フレックスタイム制とは、労働者が始業・終業の時刻を自主的に決定できる柔軟な勤務制度です。企業側が一律の勤務時間を定めるのではなく、労働者が各自の生活スタイルや業務の状況に応じて出勤・退勤時間を調整できる点が大きな特徴です。
この制度には、特に以下の2つのポイントがあります。
労働時間を「期間単位」で管理
通常の労働時間制度では、「1日8時間・週40時間」といった日単位・週単位で労働時間を管理しますが、フレックスタイム制では、1か月〜3か月の清算期間内で所定の総労働時間を満たすことが求められます。
たとえば、清算期間が1か月で所定労働日数が20日間であれば、総労働時間は160時間(8時間×20日)。この160時間を清算期間内で自由に配分できます。
始業・終業時刻を労働者が決定
出退勤時間を本人が決められるため、「今日は保育園の送りがあるから10時出社」「明日は用事があるので16時退勤」といった調整が可能です。
この柔軟性は、育児・介護中の従業員の両立支援に特に有効です。また、パート・アルバイトでも適用可能であり、多様な働き方を支える制度として導入の広がりを見せています。
フレックスタイム制の構成要素
フレックスタイム制は以下のような要素で構成されます。
| 用語 | 内容 |
|---|---|
| 清算期間 | 所定労働時間を定める期間(最長3か月) |
| 総労働時間 | 清算期間内に働くべき時間(例:160時間など) |
| コアタイム | 毎日必ず勤務しなければならない時間帯(例:10:00~15:00) |
| フレキシブルタイム | 出退勤時間を自由に決められる時間帯(例:7:00~10:00、15:00~20:00) |
※なお、コアタイムを設けない「スーパーフレックス型」も可能です。
導入手続きと具体的な記載例
労使協定(フレックス協定)の締結
労働基準法第32条の3に基づき、労使協定を締結する必要があります。協定書には、以下の内容を明記し、事業場に備え付けます。
【記載例】
- 清算期間:1か月(毎月1日から末日まで)
- 総労働時間:160時間(所定労働日数20日×1日8時間)
- コアタイム:10時~15時
- フレキシブルタイム:始業可能時間 7時~10時、終業可能時間 15時~20時
- 適用範囲:3歳未満の子を有する従業員
就業規則への記載
【記載例】
第●条(フレックスタイム制の適用)
労使協定によりフレックスタイム制を適用する従業員の始業、終業時刻については、労使協定第○条で定める始業、終業の時間帯の範囲内において従業員が自由に決定できる。
2.フレックスタイム制に関する他の項目は、別添の労使協定を就業規則の一部として当該協定に定める内容による。
実務上の注意点(導入後の運用で失敗しないために)
労働時間の把握・記録の精度が必要
労働時間を「本人の自己申告で自由に調整できる」からといって、企業側が把握を怠ってはいけません。
特に、テレワーク等と併用する場合には、PCログ、勤怠システム、チャットツールの稼働時間記録などを使い、正確に勤怠管理を行う、若しくは「事業場外みなし労働時間制」を使用しましょう。
コアタイムへの遅刻・早退の扱い
「コアタイムがあるのに遅刻・早退が続く」といったケースでは、勤務態度上の問題として別途対応が必要になる場合があります。
コアタイムの重要性、遅刻・早退時の扱い(有給消化・欠勤など)をあらかじめ制度設計の段階で明確にしておきましょう。
中抜け・私用外出の扱い
フレックスタイム制では、「中抜け」や「一時的な私用外出」は原則認められていますが、これを無制限に許すと業務に支障が出ることがあります。
そのため、労使協定等に中抜けのルールを設けると、制度が乱用されにくくなります。
パート・アルバイトへの導入には労働契約と整合を
短時間勤務者に導入する場合は、契約で定める所定労働時間・労働日数との整合性を図ることが大切です。
また、週所定労働時間が20時間を下回るような不安定な働き方になると、雇用保険の適用や社会保険の取り扱いにも影響が出る場合があるため注意が必要です。
まとめ
フレックスタイム制は、従業員の多様なライフスタイルに対応する柔軟な勤務制度として、企業にも従業員にもメリットがあります。
特に、育児・介護など家庭の事情と仕事の両立を目指す人材にとっては、就業継続の大きな後押しとなります。
また、パート・アルバイトへの適用も可能で、多様な人材の活用や人材定着に貢献する制度です。
一方で、導入・運用にはルール設計や管理体制が不可欠です。制度が形骸化してしまうと、トラブルの原因になることもあります。
なかま社労士事務所では、フレックスタイム制の導入支援、就業規則や協定書の整備、勤怠管理方法の見直しまで幅広くご相談に応じております。
「まずは対象者の設定から相談したい」「勤怠管理の仕組みまで含めて整えたい」といった場合も、お気軽にご相談ください。