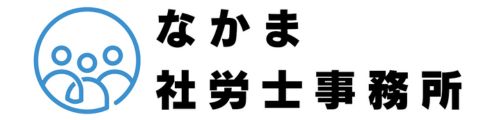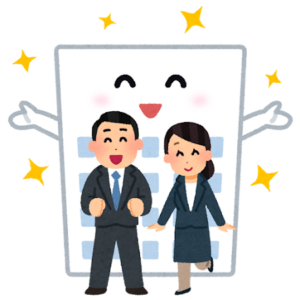【令和7年6月改正対応】熱中症と労災の関係 ― 通勤災害や事業主の対応は?
こんにちは、なかま社労士事務所の中間です。
夏場になると、熱中症に関する労災申請のご相談が増えてきます。特に令和7年6月には労働安全衛生法関連の政令・省令が改正され、熱中症対策が事業者の義務として法制化されました。
この記事では、実務に役立つよう以下の4点を順を追って解説します。
目次
熱中症は労災になるのか?判断ポイントは?
まず、「熱中症が労災として認められるか?」の判断基準ですが、重要なのは、
「暑熱な環境であったかどうか」がポイント
という点です。
たとえば以下のようなケースでは、業務との関連が強いとされ、労災と認定されやすくなります。
- 真夏の屋外での建設作業
- 空調のない倉庫での長時間作業
- 高温の機械周辺での作業 など
一方で、同じ業種・同じ日であっても、
- 作業の内容や時間
- 作業場所の暑さの程度(WBGT値等)
- 本人の体調や基礎疾患の有無
といった複合的要素をもとに総合判断されます。
「暑かったから労災になる」という単純なものではないことに注意が必要です。
令和7年6月改正~熱中症対策が事業主の義務に
令和7年6月、労働安全衛生法の政令・省令改正により、熱中症対策が努力義務から「義務」へと格上げされました。
具体的な義務内容(一部)
- WBGT(暑さ指数)の測定と記録
- 遮熱・冷却装置、空調・送風機の設置
- 水分・塩分補給の指導
- 休憩時間・作業時間の調整
- 従業員への教育の実施
対象となるのは、一定の暑熱環境下での屋内外作業。
つまり、熱中症対策は“やっておいた方がいい”から“やらなければならない”へと変わったのです。
この義務を怠ると、安全配慮義務違反として民事上の責任も問われる可能性があるため、今夏以降、対策の強化は急務となります。
通勤中の熱中症は労災になるのか?
ここで多く寄せられるのが、「通勤中に熱中症になった場合、労災になりますか?」という質問です。
この点については、
基本的に通勤災害として熱中症は認められない
というのが、実務上の取扱いです。
その理由としては、通勤中は多くの場合、電車や自動車など空調の効いた交通手段で移動しており、一般的に「暑熱な環境」に長時間さらされているとは言いがたいためです。
ただし、以下のような特殊な状況がある場合には、個別に判断される余地があります:
- 徒歩や自転車による長時間の通勤で、直射日光に継続的にさらされた場合
- 会社が指定した服装により熱がこもりやすかった場合
とはいえ、これらはあくまで例外であり、原則として通勤中の熱中症は通勤災害には該当しないという点を押さえておくことが大切です。
労災ではない場合、事業主はどう対応すべき?
熱中症の発症後、労災申請が行われることもありますが、業務起因性が明確でない場合には、事業主としての対応が問われます。
そのときの対応方法は、以下2点になります。
① 労災として認められないときは、「事業主の証明欄は記載しない」
② 「任意様式の申立書」で対応する
労災申請の書式(様式第5号等)には「事業主証明欄」がありますが、これは業務災害として認められるときに記載するものであり、通勤中や業務起因性が微妙なケースでは記載しないことが原則です。
また、事業主証明拒否についての申立書を作成し、一緒に提出することが大切です。
まとめ
- 労災の判断基準は「暑熱環境かどうか」
- 令和7年6月からは熱中症対策が法的「義務」
- 通勤中の熱中症は、原則として労災対象外
- 判断が微妙なケースでは「証明欄は書かず、申立書対応」
熱中症は予防が第一です。
義務化された対策を踏まえて、暑熱リスクを“放置しない”職場づくりがますます求められます。
ご不安がある場合は、なかま社労士事務所までお気軽にご相談ください!